海外での腎移植|適切な予後管理こそが移植腎の生着年数を左右する
帰国後のアフターケア(予後管理)はどうするの?
 「海外で腎臓移植(腎移植)を受けたはいいが、日本に帰国後は海外で臓器移植(渡航移植)を受けた患者のアフターケア(予後管理)や免疫抑制剤の処方を拒否をすると聞いている」と心配する患者さまもいらっしゃるでしょう。
「海外で腎臓移植(腎移植)を受けたはいいが、日本に帰国後は海外で臓器移植(渡航移植)を受けた患者のアフターケア(予後管理)や免疫抑制剤の処方を拒否をすると聞いている」と心配する患者さまもいらっしゃるでしょう。現に多くの大学病院等では、2008年に加盟各国によって批准されたイスタンブール宣言(渡航移植の原則自粛)を根拠に、HP上で「診療を拒否する」と公式に表明しています。
| ◆このページの情報でご理解いただけること◆(読了時間:約5分) ・医療を求める患者に対する医師の応召義務 ・海外移植患者は診療拒否にあう? ・厚生労働省が公表した、海外渡航移植患者の実態調査報告の詳細 ・帰国後のケア(予後管理)をお願いできる専門医の確認 ・過去に腎移植を済ませた患者さまから体験談を聞く |


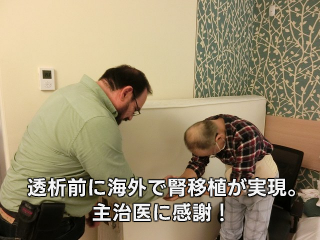
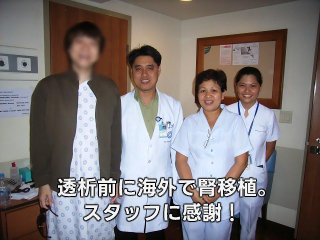

web上には「海外渡航移植を受けられた患者さんへ」などのタイトルで「帰国後の診療を拒否する」と多くの大学病院が診療拒否を表明しています。
しかし不思議ですね。これほど多くの医療機関が診療拒否を表明しているにもかかわらず、渡航移植を済ませて帰国した大勢の患者さんは、どこで予後管理を受けているのでしょうか?
帰国後に専門医を継続受療している渡航移植を済ませた患者数(厚生労働省2023年発表)
厚生労働省の発表によると2023年3月時点で、渡航移植を受けたあと日本に帰国して、国内の医療機関で予後管理のために外来診療を受けている患者数は全国で543人とのこと。「海外渡航移植患者の実態調査」しかしこの人数には、厚労省から調査・回答を求められていない医療機関や、回答を求められても非回答だった医療機関に通う患者数は含まれてはいませんから、実数はこんなに少ない人数ではないはずです。
そして、厚労省の調査結果を深く掘り下げて分析した移植学会会員の医師によると「全国で多くの渡航移植患者さんが、診療を拒否されずに受療している」と述べておられます。「渡航移植後の患者の診療実態」
医師には患者を診療する「応召義務」が国から課されているにもかかわらず、現に診療拒否を公言している施設もあるため、海外で臓器移植手術を受けようとする患者さんにとって、帰国後のケアに関する心配は大きなものがあると思います。しかし私共が知る限り、皆さん誰ひとりの例外もなく豊富な経験を有する移植専門医の手厚いアフターケアの下、免疫抑制剤 の調整・処方を受けておられます。
その免疫抑制剤の血中濃度は、一定の範囲内に収まるよう調整が必要なため、素人判断は出来ません。
帰国後にも薬の調整や各種の検査が1~3ヶ月に一回ほどありますが、移植後は「厚生医療」が適用されるため、薬代を含む医療費の自己負担は、高額所得者でも月に最大で2万円程度。(自治体によって若干の開きがあるようです)
術後の管理こそが移植腎の生着年数を左右する
臓器移植の歴史の中で世界で最も最初に行われたのが腎臓移植です。当初は実験的医療の範囲にとどまっていましたが、術式が確立した現在、移植手術の外科的成功率はほぼ100%となっているようです。
しかしこの成績だけで喜んではいけません。術後に最も大切なことは、専門医による適切な予後管理がなされることです。適切な予後管理こそが、移植腎の生着年数を左右すると言っても過言ではありません。
専門医は長年の臨床経験や蓄積された研究結果により、患者さんにとっては「異物」である、移植された腎臓が引き起こす免疫反応を熟知していますから、その移植腎が長持ちするように免疫抑制剤を調整します。
その免疫抑制剤は飛躍的な進歩を遂げて、臓器移植医療には欠かせない予後管理を担っています。外科手術が成功するのは当たり前と言ってよいほど外科領域は進歩していますから、手術そのものに大きな心配は不要と思われます。しかし術後の予後管理こそが一番大切なことと、心にお留め置きください。腎臓は、あらゆる臓器の中で最も敏感に免疫反応を示す臓器なのです。
もしも薬を飲み忘れたら
数種類の免疫抑制剤には、一日に1回服用するものもあれば、おおむね12時間ごとに一日に2回服用するものもあります。
これらの薬を万一、飲み忘れてしまったら次のように対処してください。
例えば朝9時と夜9時に飲むべき薬の、朝の服用を忘れた場合、その飲み忘れに気付いた時刻が午後3時前であれば、すぐに「朝の分」として服用します。しかし飲み忘れに気づいたのが午後3時以降であったら、その飲み忘れた「朝の分」は飛ばして(飲まずに)夜の9時の薬だけ服用します。このとき決して夜9時に朝の分も一緒に飲むようなことはしないでください。
つまり12時間ごとに服用する薬を飲み忘れたら、その飲み忘れに気づいたのが本来の服用時間の6時間以内ならば、気付いた時点で服用し、6時間を過ぎて気付いたらその分は飲まずに、次の服用時間に飲むべき薬だけを飲むようにしてください。
免疫抑制剤の血中濃度を測定する通院日は
そして専門医の診察のために通院する際は、病院の検査室で薬の血中濃度を測定して、その結果に基づいて免疫抑制剤の量を調整します。したがってこの検査通院の日は、医師から特に指示がない限り、朝の薬は服用せずに受診するようにしましょう。
免疫抑制剤と一緒に口にしてはいけない果物やジュース
以下の果物やそのジュースは、免疫抑制剤の血中濃度を異常に上昇させる相互作用がありますから、口にはしないでください。・グレープフルーツの果実とそのジュース
・はっさく、夏みかんなどの柑橘類も、果実・ジュースともに避けてください。
一方で、みかんやレモン、カボスなどは大量に食べなければ相互作用はないと言われています。
帰国後のアフターケアがご心配でしたら、心ある医師のケアを実際に受けている患者さんのお話をお聞きになられてはいかがでしょうか。電話でも、直接お会いになってでも、ご自身の体験や近況をお話しくださいます。
さらにご不安でしたら、移植手術のために現地に渡航する前に前述の医師を訪ね、専門医ならではのアドバイスを求めてはいかがでしょうか。(ただし、保険を使っての通常の診療費は発生します)
この医師の診察室前の待合室には、海外で腎臓移植を済ませて帰国した渡航移植患者が、常にご自分の診察の順番を待っておられます。
すべてをお知りになれば、帰国後の予後管理についての懸念はなくなり、安心されることでしょう。
ご相談は無料でお伺いいたします。
03-4283-7042(電話) または
080-7841-8989(医療通訳直通携帯)までお気軽にどうぞ。
◆深夜・早朝等を除き、週末や祝祭日も毎日ご相談を承っております◆
(所用で事務所を空けていることもありますので、まずは直通携帯電話をご利用ください)
万一お電話を受けられなかった場合は、必ず折り返しご連絡させていただきます。



